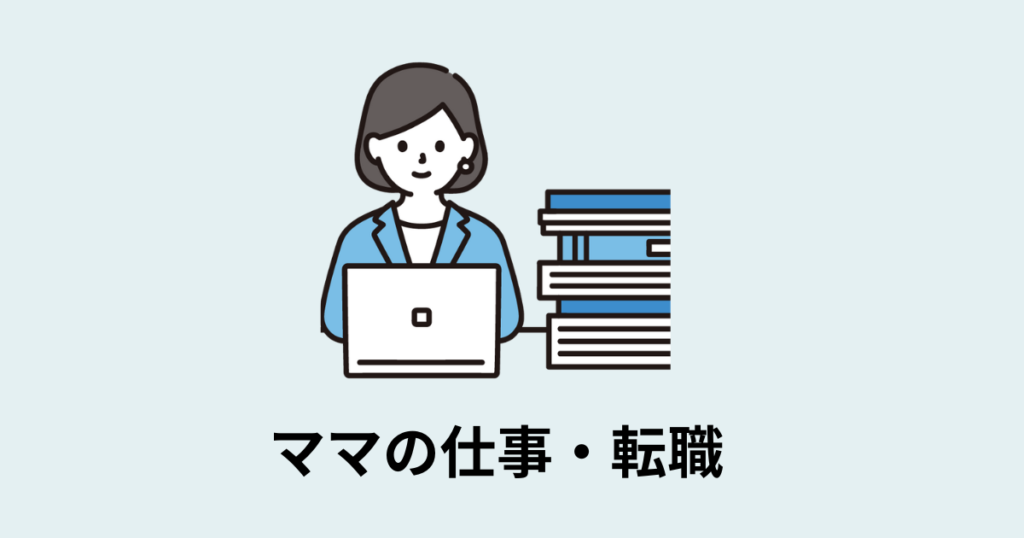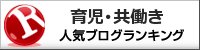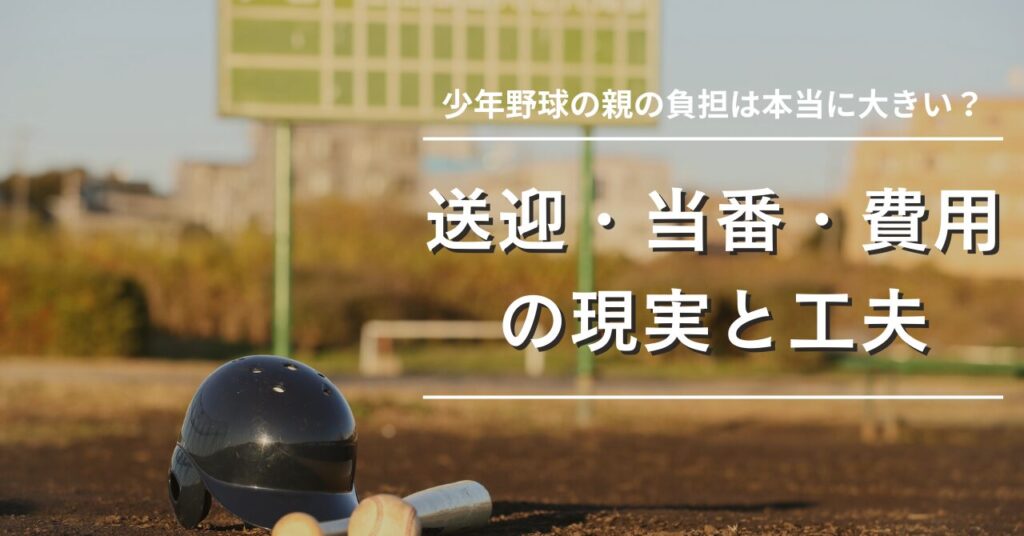
「少年野球は親の負担が大きい」と耳にしたことはありませんか?
たしかに、実際に入団してみると、送迎・当番・費用など、想像以上に大変と感じる家庭も少なくありません。

スポーツの中でも野球って親の負担が大きいイメージがなんとなくありますよね。
ただ、実際にはチームによるというところが大きいという点も忘れてはいけません。
そのため、見学や体験でみるポイントと質問するために、どういったことが負担になるのかイメージしていきましょう。
この記事では、少年野球に関わる親の負担をリアルに解説しつつ、共働き家庭でも無理なく続ける工夫をご紹介します。
少年野球で親の負担が大きいと言われる理由

これが負担…
- 送迎の頻度と距離
- 当番制(お茶当番・練習補助・遠征)
- ユニフォームや道具、会費などの費用
送迎の頻度と距離
少年野球チームは、週末や祝日に練習・試合が組まれることが多く、送迎の回数が非常に多いのが現実です。
- 土日両方とも練習や試合
- 平日夜の自主練習
- 遠征や練習試合
例えば、車で片道20〜30分のグラウンドまで送迎するとなると、親の時間的負担はかなり大きくなります。
特に兄弟がいる家庭では、下の子を連れて行くケースも多く、「一日中グラウンドに拘束される」ことも珍しくありません。

チームによっては一日見学をするというパターンもありますが、みんな送ったら、次は迎えまでは解散パターンも最近では多いようです。
ただ、試合の時には保護者が観ている人も増えます。
我が家では毎週というわけではありませんが、熱中症の心配もあるので夏は練習を観ておく場合もあります。
当番制(お茶当番・練習補助・遠征)
少年野球には、親が関わる「当番制」が今も多く残っています。代表的なものは以下の通りです。
- お茶当番:選手や指導者に飲み物を準備する
- 練習補助:ボール拾いや準備・片付け
- 遠征付き添い:試合会場までの移動サポート
地域やチームによっては「お茶当番廃止」の流れもありますが、まだまだ残っているチームもあります。
グラウンドの近さなどもチームを選ぶ点では重要ですよね。
チームによっては、親が土日に丸一日グラウンドにいるのが当たり前、という空気が負担に感じる方も多いです。
チームの雰囲気や、体験に行ったときに保護者がどの程度いるのかもチェックしておくとよいですね。

息子のチームはお茶当番はないのですが、この酷暑で熱中症が心配なのでお母さんが交代で夏だけ見ていることが多いです。
個人的にしているだけなので、できない場合は特にしなくても問題なさそうです。
私も下の子がいる時には、他の方に任せる場合もあります。
ユニフォームや道具、会費などの費用

少年野球は「公園で遊ぶ延長」とは違い、道具やユニフォーム、会費など様々なお金がかかります。以下に一般的な費用の目安をまとめました。
| 項目 | 費用の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 入団費 | 2,000〜10,000円 | チームによる |
| 月謝(運営費) | 1,000〜5,000円 | グラウンド使用料・備品代など |
| ユニフォーム | 10,000〜20,000円 | 上下・帽子・ソックス、ベルト込み |
| 野球用具(バット・グローブ・スパイク) | 15,000〜40,000円 | メーカーや品質によって差 |
| 遠征費・交通費 | 月1,000〜5,000円程度 | ガソリン代や駐車場代含む |
| 合宿・大会費 | 5,000〜30,000円 | 年1〜2回あるチームも |
👉 初期費用は 3〜5万円程度、その後も毎月の会費や用具代で 年間10万円以上かかるケース も珍しくありません。

月謝はチームによりばらつきはありますね。
でも私が周辺のチームを確認しても高くて4000円程度、安ければ1000円と他の習い事と比べると破格の価格でしたね。
スパイクは統一感を出すために指定のチームが多いです。
しかし、バットや、グローブはピンキリなので、自分のレベルに合う物を選べばよいと感じます。
合宿や、退会費用もチームによって違うので、見学時などに確認しておくとよいですよ。
負担感は少年野球チームによって違うってどういうこと?

チームによっての違い
- お茶当番はないところもある
- 連盟に所属していない場合がある
- 指導者が多い
- 練習環境が整っている
- 送迎に積極的な保護者が多い
- 雰囲気的にずっと付き添わなければいけないということがない
連盟に所属していないってどういうこと?って私自身も思っていました。
少年野球には大きな連盟があるのです。
正式名称と意味
JSBB=Japan Soft Baseball Boysで日本少年野球連盟(日本少年野球協会)の略称です
これに入っているのと、いないのとではかなり状況は変わる可能性があります。
例えば、野球育成解決サイトFirst-pitchの記事をご覧ください。
連盟無所属で「子どもの笑顔増える」 古い学童野球に懸念…創部2年目で“部員急増”のワケ
このように連盟無所属のチームなら負担感は減る可能性があります。
ただ、大きな大会にはでられないというデメリットはありますね。

実際に私の息子が所属するチームも連盟無所属です。
大きな大会には出られませんが、それなりに試合もあります。
共働き家庭が直面しやすい悩み

共働き世帯では、以下のような悩みがよく聞かれます。

- 送迎時間が仕事と重なる(試合が朝早くから始まる、夜練習がある)
- 当番制が調整できない(夫婦どちらも土日勤務がある場合など)
- 下の子の世話と両立が難しい
- 休日が少年野球でつぶれてしまい、家族の時間が減る
子どものために頑張りたいけど、生活リズムや仕事に支障が出ると「続けるのが難しい」と感じることもあります。

私もシフト制んお仕事をしていたのでわかるのですが、土日、仕事がある職種の方は確かにかなりしんどくなります。
そのため、チーム選びは慎重に行くべきですね。
また、下の子がいる場合にも、休日すべてが少年野球で埋まってしまうのが嫌だという場合も、負担が大きいチームは避けた方が良いでしょう。
親の負担を軽くする工夫アイデア

色々考えてたら、負担デカすぎない?無理じゃない?って躊躇する気持ちわかります。
でもある程度解決できるところもあるので、どうすれば負担は軽くなるのか?をシェアしていきますね。
送迎のシェア・相乗り制度

常に自分の子は自分で送迎しないといけない!と思うかもしれませんが、そんなことはありません。
実際には、その日に車で送迎をできる家庭が送ってくれることも多いです。
もちろん、逆に送迎を行うこともあるのですが、近所の子を乗せるスペースさえあればそれほど負担感は大きくはありません。
ポイント
- 同じ地域に住む家庭で 送迎を交代制にする
- 兄弟のいる家庭と 相乗り してガソリン代を節約
- チーム全体で 送迎ルールを整備 すると不満が減りやすい
特に共働き家庭は、他の保護者と協力関係を築くことが重要です。
いつも乗せてもらうことが多いとなった時に、コミュニケーションを取っておいてお礼をしっかり言う、何か差し入れを入れるなど気遣いがあればもっと良いとは思います。
周囲との調整という面では仕事と似ている部分もあるので、仕事と割り切ってしまうのも一つです。
当番制の見直し

我が家の近くのチームはほぼお茶当番がないところが多かったです。
1チームだけお茶当番があるとのことだったのですが、そのチームは保護者の負担感が強すぎて…とチームをうつる保護者もおられましたね。
ポイント
- 「お茶当番廃止」のチームを選ぶ
- 役割を細分化し、1家庭あたりの負担を軽減
- 当番が難しい場合は、金銭で代替(例:飲料費をまとめて支払う)
最近は「親の負担を最小限に」という方針のチームも増えています。
入団前に確認しておくのがおすすめです。
費用を抑える方法
野球道具って実際めちゃくちゃ高い物もあるんですよね。
グローブは消耗費でもあるので、メンテナンスさえきちんとすればそれほど高い物でなくてもある程度使えます。

スパイクや練習着、ユニフォームなどはチームで保管しているところもあり、息子のチームはサイズさえあればもらえました。
- 中古のグローブやバットを利用(メルカリ・リユースショップ)
- チームや地域の お下がり制度 を活用
- 合宿や遠征は 参加自由かどうか確認
- 高額なメーカー品でなく、初心者用セットから始める
少年野球は成長とともに用具サイズも変わるため、初めから高価なものを揃える必要はありません。

成長期はすぐに大きくなりますからね。初期費用はそれほど奮発しない方がいいです。
まとめ

少年野球は、子どもにとっては体力や仲間との絆を育む素晴らしい経験ですが、親にとっては「送迎」「当番」「費用」といった負担も現実です。
特に共働き家庭では、チーム選びや送迎シェアの工夫が欠かせません。
無理のない範囲でサポートしつつ、子どもの成長を見守ることが大切ですね。
私の息子が通うチームでも、送迎についても、車を持っていない、運転ができないなどの理由で担えない人もいます。
そのため、保護者達はできる人で、交代で送迎や見守りを行っています。
それが特に不満になっていることもないので、チームカラーを見極めて入団してみると良いかなと感じます。

実際には、入ってみないとわからない…という場合もありますが、そうなれば別に辞めてしまっても良いと私は感じます。
親の負担が続けば、子どもにも悪影響ですし、楽しく通えるチームをさがしてみるというのも一つの手段だと思います。
また、小学校の間はゆるめのチームに入り、野球の楽しさを覚えてもらい中学からしっかりやるという手段もありますよね。
でも、野球をやっていて、楽しそうな姿意外にも、悔しがっているところ、喜んでいるところこういった子どもの姿をみることができ、真剣に取り組んでいるんだなと実感できれば、応援のし甲斐もあるかもしれませんよね。
チームスポーツであり、道具の管理や練習に対する態度など子ども自身が色々と学べるスポーツ。
それが野球の良さだと感じます。