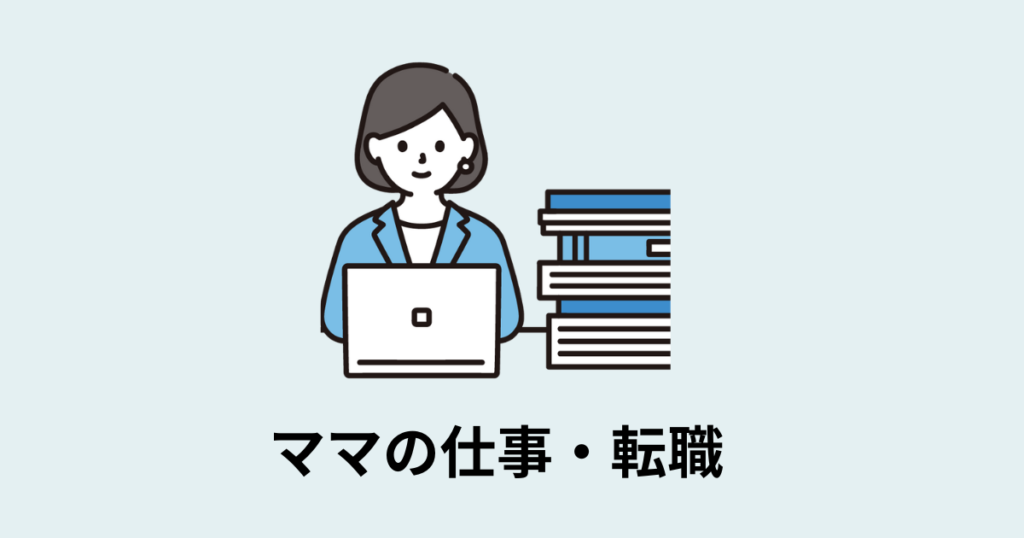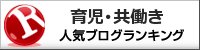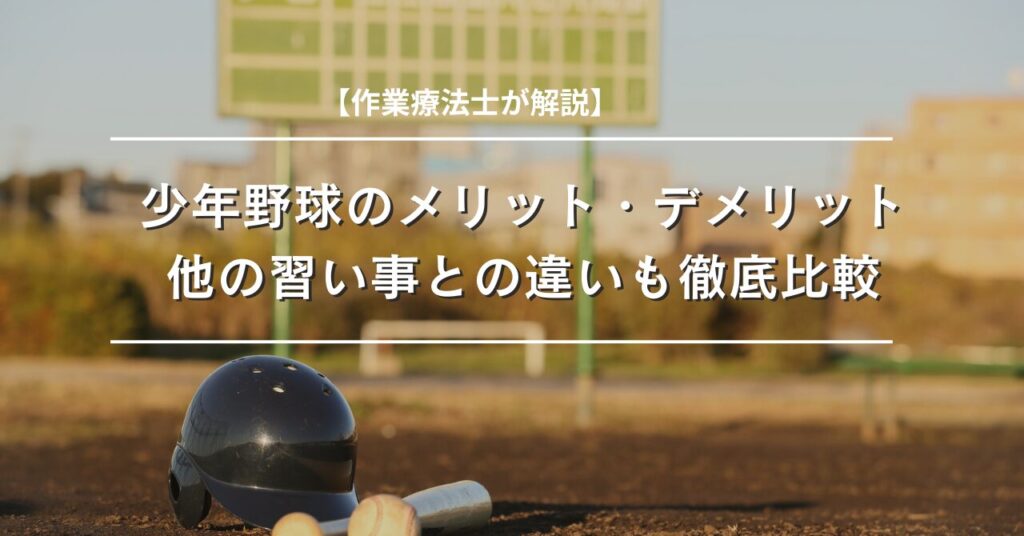

「子どもにどんな習い事をさせたらいいのかな?」
「野球は人気だけど、親の負担が大きいって聞くし迷う…」
そんな声をよく耳にします。
特に男の子の習い事として定番の少年野球。
体力や協調性を育てられる一方で、費用や親の関わりが大きく、続けるのが大変だという声も少なくありません。
私は作業療法士として、運動や作業活動、動作の分析、集団の力について学んだ経験があります。
今回は作業療法士的な視点も交えて、少年野球のメリット・デメリット、そして他の習い事との比較について解説します。
少年野球のメリット

全身を使った運動で体力・基礎運動能力が育つ
野球は「投げる・打つ・走る・捕る」といった多様な動きを組み合わせるスポーツです。
特定の筋肉だけでなく全身を使うため、体力や運動能力の基礎を幅広く育てられます。
特に、投げる動作で肩・腕の協調性が、打つ動作で目と手の連動(眼と手の協応性)が鍛えられる点は、他のスポーツにはない特徴です。
また、投げるには体幹や下肢の安定性、体幹を固定しながら四肢を動かす訓練になります。
上半身だけでなく、必ず下半身を連動して使う訓練になりますね。

打つ動作は道具を自分の体の延長として扱うイメージで、難しい動作でもあります。
そういった経験ができるのは、野球ならではですし、バットでボールを打ち返せるような動体視力を鍛えれば、どんなスポーツでも視覚的に不利になることは少なくなります。
チームスポーツだから協調性や社会性が身につく

野球は9人でプレーする団体競技です。
ポジションごとの役割を理解し、仲間と連携してプレーする経験は、協調性・社会性・責任感を育てます。
また「声を出す」「サインを理解する」など、コミュニケーション能力を自然に鍛えられる点も魅力です。

野球のルールを覚えるのはかなり頭を使います。
今どんなプレーが行われているのか瞬時に判断することや、この場面ではこういったことを予測する必要があるなど、かなり頭を使うスポーツでもあります。
また、プレーで貢献できなかったとしても、声を出せる選手は貴重です。
声を出すことで士気があがる経験があれば、学校でも必ず役に立ちます。
そして、自分を客観視するということも必要になります。
自分はどこが長所なのか、自分がこのチームでどのポジションへ行けばゲームを優位に進められるのか、自分を客観的にみつめる訓練にもなります。
低学年の時には、自分を客観的にとらえることはかなり難易度が高いです。
そのため、親と一緒に対話をすることでも語彙力、自分の気持ちを伝える表現力、相手の意見を聞く力など様々な物が備わってきます。

親としてもコミュニケーション面で成長したなと感じる場面はでてきます。
そして、それは社会に出ても対話をすれば解決できるという経験につながります。
集中力や忍耐力が鍛えられる

野球には「待つ時間」が多いという特徴があります。
バッターの順番を待つ、守備中にボールが来るのを待つ。
こうした時間を通じて、集中力を維持する力や忍耐強さが養われます。
これはサッカーなど常に動き続けるスポーツにはあまりない発達効果です。

サッカーやバスケの場合は常に動き続けます。
野球の待つ時間をどれくらい集中できるかというのは、大切な要素です。
低学年の時には試合をしていても、集中が切れてしまって、ボールの行方を追っていなかったなんて場面もありますが、試合慣れをすることで、徐々に集中できるようになります。
親子のコミュニケーションが増える
練習の送迎やキャッチボールの相手をする機会は、親子の会話や関わりを自然に増やしてくれます。
「子どもと共通の話題ができる」「応援を通じて子どもの頑張りを共有できる」というのは、少年野球ならではのメリットです。

親としては多少の負担はあるのですが、子どもが頑張っている姿を見たいと思っている人も多いのではないでしょうか。
キャッチボールなどはできない…と不安なママでも、食事を工夫したり、生活面を整えたりのサポートはできるので、規則正しい生活を送るきっかけにもなります。
少年野球のデメリット・注意点

親の負担が大きい(送迎・当番・費用)
少年野球では親が試合や練習の送迎をすることが多く、さらに「お茶当番」「大会運営の手伝い」など保護者の役割が決められているチームも少なくありません。
また、ユニフォームやバット、グローブなどの用具代もかかるため、金銭的・時間的な負担が大きいのが現実です。
詳しくはこちらの記事を確認してみて下さい。
少年野球の親の負担は本当に大きい?送迎・当番・費用の現実と工夫
肩や肘の故障リスクがある
投球動作は肩や肘に負担がかかりやすく、投球障害(野球肘・野球肩)に悩む子もいます。
特に成長期の骨や関節はまだ未発達なので、練習量やフォームに注意が必要です。

低学年ではピッチャーも1試合に60球と投球制限が決まっています。
でも練習も含めると結局100球近くなげているのでは?と感じます。
そもそもの練習量の見直しや、投げ方の指導。アイシングやリラクゼーション、メンテナンスは必要になってきますね。
練習や試合のプレッシャーでストレスになることも

団体競技ならではの「エラーして迷惑をかけたらどうしよう」というプレッシャーは、子どもにとってストレスになることもあります。
楽しむことより勝敗が重視されるチームに入ると、子どものモチベーションが下がり、途中で辞めてしまうケースも見られます。

チームカラーによってもかなり違うと感じています。
常に指導者が怒っているチームもあれば、逆に緩すぎてなあなあになってしまうなど様々なチームカラーがあるので、子どもはどんな場所にいれば成長できるかを考えて入団しましょう。
家庭は安心の場で、野球の結果についてあまり厳しく言わない方が良いのかなと個人的には思っています。
団体競技が合わない子には続けにくい
感覚が敏感な子や、自分のペースで活動するのが好きな子にとっては、団体競技のルールや空気に合わせることが苦痛になることもあります。
「向き・不向き」がはっきり分かれるのも少年野球の特徴です。

これもチームによってはついていけるというチームもあると思うんです。
特に低学年の間には集中が続かなかったり、すねてしまったりすることがあります。
そういった時にどのような指導で導いてくれるのかという点は指導者によっても違います。
また、親の声掛けによっても、子どもの受け取り方は変わってくるので、指導者にきつく言われているのに、さらに追い込むように保護者が思いを伝えてしまうと辞める原因にもなってしまいますよね。
作業療法士が考える「少年野球に向いている子・向いていない子」

- 向いている子:体を動かすのが好き、協調性を育てたい、仲間と一緒に何かをするのが楽しいと感じるタイプ
- 向いていない子:感覚過敏で音や声が苦手、マイペースに取り組みたい、団体行動に強いストレスを感じやすいタイプ
これは「良い・悪い」ではなく、子どもの特性に合っているかどうかの問題です。

正直ある程度の身体的な機能は、後からでもどんどんつくと思うんです。
特に運動神経発達の時期と言われるゴールデンエイジ9歳から12歳程度の時には、野球練習だけでなく様々な体の使い方を訓練していくことで発達していきます。
合うか合わないかは、性格的な因子が大きく関与します。
ただ、性格的には向いていないように見えても、やってみると意外に楽しんでできるという場合もあるので、金銭的に問題ならやってみて考えるというのも一つの手です。
また、性格的にも向いていて、野球が大好きでも、環境に寄って大きく変わると感じています。
例えば指導者の指導が高圧的で納得できない、チーム内での人間関係でどうしても合わない人がいる、いじめのようなことが起こっているなどです。
そういった時には、野球ではなくそのチームの環境が合わなかっただけだと切り替えていくことも必要です。
少年野球と他の習い事の比較
次は野球と他のスポーツで比較しながら違いを検討していきます。
少年野球 vs サッカー、バスケ
少年野球 vs サッカー
- 共通点:協調性、ルール理解、体力づくり
- 違い:野球は「待つ集中力」、サッカーは「動き続ける持久力」
- 向いている子:観察力や思考力がある子は野球、活発で動きたい子はサッカー

サッカーは体力面や走力ではかなり秀でているスポーツですよね。
普段意識していない足を、手のようにコントロールできるようになるという訓練は、運動発達にはとても有意義だと感じます。
公園などでもボール一つで楽しめるという点もサッカーの魅力かなと感じます。
サッカーやバスケのようにコンタクト(体が当たる)ことがないのも野球の魅力です。
体を当てるようなスポーツでは恐怖心を感じる子や、体格差が比較的問題にならないのも野球の魅力です。
少年野球 vs 水泳
少年野球 vs 水泳
- 共通点:基礎体力の向上
- 違い:野球はチームでの協力、水泳は個人での達成感、野球はケガをする可能性もある。水泳は少ない。
- 向いている子:集団が得意なら野球、自分のペースで努力したい子は水泳

水泳はどんなスポーツをするにも基礎としてやっているお子さんは多いです。
怪我のしにくさ、左右対称に動かすことで均等な筋バランスを手に入れることができます。
また、タイムを競い合うので、自己ベストがしっかり目に見えてわかるという点で、自分のペースを持っている子には良いでしょう。
少年野球 vs 体操
少年野球 vs 体操
- 共通点:運動能力の基礎を養える
- 違い:野球は複合的な動き、体操はバランス感覚・柔軟性
- 向いている子:仲間と協力する経験をさせたいなら野球、体の操作を極めたいなら体操

もしかしたら体操以上に、自分の体のコントロールを学べる種目はないかもしれませんね。
野球は道具を使うという点で、それらを手の炎症のように扱うダイナミックタッチと呼ばれるような物体の大きさや向き、重さを知覚する能力も鍛えることができます。
少年野球 vs 武道(空手・剣道など)
少年野球 vs 武道(空手・剣道など)
- 共通点:礼儀や精神面を育てられる
- 違い:野球はチームプレー、武道は自己コントロール
- 向いている子:仲間と成長したい子は野球、集中力や自己抑制を伸ばしたい子は武道

武道はより野球以上に礼儀を重視します。
少年野球 vs ピアノ・学習系習い事
少年野球 vs ピアノ・学習系習い事
- 共通点:継続力を養える
- 違い:野球は体力や社会性、ピアノや塾は知識・技能
- 向いている子:体を動かしたい子は野球、机に向かうことが得意な子は学習系。両立は可能。

チームさえ選べば、土曜日は休んで塾へ行くという人もいますよ。
学習系の習い事とは比較的両立しやすいです。
まとめ|少年野球のメリット・デメリットを理解して選ぼう

少年野球には「体力・社会性・忍耐力が育つ」という大きなメリットがある一方で、「親の負担・ケガリスク・子どもによっては続けにくい」というデメリットもあります。
大切なのは、子どもの特性や性格、家庭の環境に合っているかどうか。
他の習い事と比較しながら、「わが子にとって一番プラスになる選択」をしてあげましょう。
また、チームの方針によって大きく変わることもあるので、負担が大きいと感じる場合はチームを選び直すと良いでしょう。
まずは楽しく野球が続けられるようなサポートがあると、子どもは続けやすいのではないでしょうか。