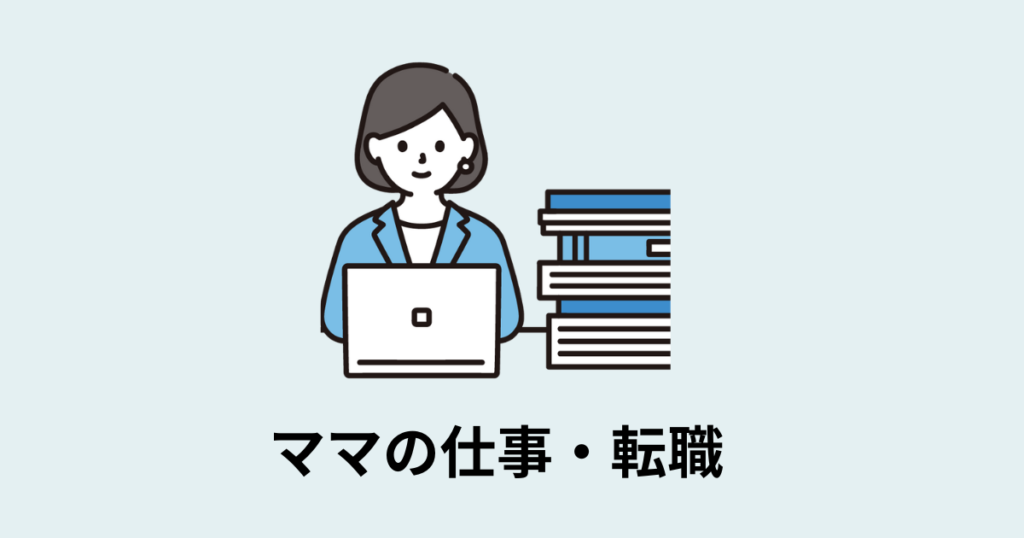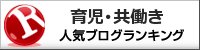子どもの手先の発達は、将来の学びや生活につながる基礎をつくるとても大切な要素。
中でも巧緻性(こうちせい)と呼ばれる「手先の器用さ」は、遊びの中で自然に育てることができます。

子どもの保育参加でも感じるんですが、手先の器用さって子どもによってもかなり違う。
もちろん生まれ持った違いもありますが、経験による違いも出るんです。
この記事では、2児を子育て中であり、作業療法士である私が選んだ「指先遊び」グッズを紹介します。
集中力や想像力を引き出すおもちゃ、家庭でできる工夫も合わせてご紹介。
巧緻性ってなに?子どもの「手の発達」に必要な理由

巧緻性って初めて聞いたという方もおられるかもしれませんが、作業療法士の中では非常によく使うワードです。
巧緻性は体幹の使い方や、手と手の協調性、手と目の協調性など様々な要素が組み合わさって機能するものです。
様々な要素が関係するからこそ、手を使って遊んだ経験は非常に大切なんです。

手をつかうというのは脳を使うということです。
脳の運動野において手の領域は非常に広いです。
0〜3歳の手の発達段階
赤ちゃんの手の発達は驚くほど早く進みます。以下に、月齢ごとの発達目安をまとめました。
| 月齢 | 手の動きの発達内容 |
|---|---|
| 生後0〜3か月 | 握る(反射的)・拳を握っている |
| 生後4〜6か月 | おもちゃに手を伸ばす・にぎる |
| 生後7〜9か月 | 両手を使って遊ぶ・落ちた物を拾う |
| 生後10〜12か月 | 親指と人差し指でつまむ・物を出し入れする |
| 1〜2歳 | ボタンを押す・引っぱる・ねじる動作が増える |
| 2〜3歳 | クレヨンで線を引く・積み木を重ねる |
この時期にいかに適切な刺激を与えるかが、発達に大きく関わります。

今できないけれど、繰り返しているうちにいつのまにかできるようになっていたという経験が、子を持つママなら多いですよね。
でもそれってお子さんがいっぱい遊んで学んだことの一つかもしれませんよ。
手先を鍛えることで得られる効果

巧緻性が高まることで、伴って得られる効果があるんです。
以下のような効果が期待できます
手先を鍛えたら…
- 自分で食べる・着替えるなどの日常生活動作(ADL)の自立
- お絵描きや工作への集中力アップ
- 遊びや作業を通した創造力・達成感の獲得
- 小学校以降の鉛筆操作・ノート書きへのスムーズな移行
自分でできることが増えることで、自信にもつながってどんどんやってみようという気持ちも生まれます。

赤ちゃんの時の経験が、小学校になっても好循環を作ってくれるんですよね。
おすすめの指先あそびグッズ

作業療法士ママが子どもに与えてよかったと思えるアイテムを、年齢別・目的別に紹介します。
もちろん、これ以外にも様々な巧緻性を鍛えるグッズが有効です。
つまむ・にぎる・ねじるを育てるおもちゃ
くもん出版「くるくるチャイム」
ボールをつかんで落とす動きが楽しく、つまむ・握るの力が自然と育つ。
肩関節の動きも使うので、座ている姿勢を保持することの練習にもなりますよ。
ボーネルンド「ビーズコースター」
ビーズを動かすことで、指先の操作と空間認知が育まれる。

つまみながら動かすって、関節を制御する数が増えるので難しくなります。
色もカラフルなので、視覚的な刺激や言語活動にも有効です。
ねじねじつみき
組み立てる・外す・ねじるの3ステップで手指の動作を強化。

物をねじる動きって日常生活でも蛇口をひねるときや、瓶を開ける時などあるんですが、赤ちゃんにその経験って少ないですよね。
最近の子は蛇口も回すタイプではないので、握力や指先の力がなくできないという場面も多いようです。
高度な動きにはなるのですが、こちらはおもちゃの大きさが思っているより大きいので、行いやすいです。
1歳程度ではまだ早い子が多いでしょうが、1歳後半から2歳ごろでは使えるようになっているのではないでしょうか。
アンパンマン「かさねていれてつみつみボックス」
積む・並べる・かさねる動きが多く、親子で楽しみながら遊べる。

座ってスタートして、最終的に立って物をつかんで調整して置くという作業ができます。
動作に難易度が設定できるのがいいですね。
オーボールラトル
- 赤ちゃんから使えて安全性が高く、ガラガラの役割もある
- 指先が引っかかりやすいデザインで、早くから投げるという動作も体験できる
赤ちゃんから長く使えるおもちゃです。4歳の今でも投げるようにもっています。
素材感硬すぎず柔らかすぎずで家の中でなげてもダメージが出にくいです。
毎日続けられる家庭での工夫(身近なもので代用もOK)
おもちゃも紹介しましたが、実は高価なおもちゃがなくても、日常の中でできる工夫はたくさんあります。
例えば
- 洗濯ばさみで「つまむ力」を強化(紙にピンチをはさむ遊び)
- ペットボトルキャップで「ひねる動作」を体験
- スポンジを水にぬらして「ぎゅっとにぎる」遊び
- お米や小豆を使って「豆移し」遊び(スプーンや手で)
- 新聞紙ちぎり → 丸める → 投げるで「3段階遊び」

日常で使っている物や、100円ショップの物を使っても十分巧緻性の向上を促すものはありますね。
市販されているおもちゃの良さは、安全基準が満たされているため誤飲防止や素材の質などの心配が少ないというところではあると思います。
自分でやってみる時には、危なくないかな?という視点は持っておくことをおすすめします。
作業療法士ママが使っている商品レビュー
実際に使用して「これはよかった!」と感じた商品をご紹介します。
ピタゴラス(学研)
- 対象年齢:1.5〜
- 磁石の力で簡単にくっつくので、手先が不器用でも遊びやすい。
- 空間認識力、構成力、指先のコントロールが育つ。

最初は単一の形の物を積んだり、くっつけたりする遊びだったのが、立体的にしたり迷路にしてみたり、何か転がしてみたり遊びに広がりのあるおもちゃだなと感じます。
誤飲の事故は近年多かったようなので、そのあたりは注意です。
アンパンマンよくばりボックス
- 対象年齢:8か月〜3歳ごろ
- 散らばらないので安心して小さい子にも与えられるおもちゃ
- 押す、つまむ、引っ張る、つまみながらあける、同じ形を目で見ながら入れる、など様々な手の動きが組み込まれているおもちゃ。

アンパンマンのよくばりボックスは結構長く使えました。
そして頑丈で、壊れないので子どもふたりともに使えました。
まだ使えるので、最近やっと保育園に寄付しました。
LEGO デュプロ
- ブロック遊びは一度はやりたいNO1
- 手の巧緻性だけでなく、集中力や想像力も高まる

ブロックなら何でもいいと思うのですが、小さいタイプは大きくなってからはいいのですが、長く使えるのはデュプロだなと思います。
ただブロックをつくるだけでなく、剣をつくったり、輪投げの的をつくったり大きい物もつくることができます。
おもちゃこれだけでいけるんちゃうか?と思ったことあります(笑)
ニューブロックや、カプラやラキューもおすすめ。
ニューブロックも保育園でよく遊んでいました。
横つまみが苦手でカギをうまくあけられないなと感じる場合には、ジスターもおすすめ。
紐もついてきて、真ん中の穴に紐遠しも経験できます。保育園でも良くやっていますね。
色彩感覚や、手と目の協調性を育てるにも活躍できるおもちゃだと思います。
平べったい形ですが、立体も作れて、意外になんでもつくれます。

我が家では、ブロック系のおもちゃはTVの下に設置していつでもできるようにしています。
散らばりますが使っている間は散らかしてもOKです。
まとめ|遊びの中で「できる」を増やそう
指先の発達は、子どもが「自分でできた!」という喜びを感じるための大切なステップです。
作業療法士の視点から見ると、遊びを通して自然に鍛えることがもっとも効果的。

小学校になってからも思いますが、子どもがやらされている感を感じないようにできるかがポイントですよね。
子どもの場合は、楽しいを積み重ねていたら自然にできるようになっているというのが理想です。
小学校に入って1年生で鉛筆の持ち方を習うと思うのですが、こういった指先の遊びがその土台にもなるので、学習にも非常に大切です。
ポイント
- 巧緻性は将来の生活・学習に深く関係する力
- 0〜3歳の時期は、遊びを通じて発達の土台を作るゴールデンタイム
- 市販のおもちゃだけでなく、身近な道具でも十分にトレーニング可能
- 作業療法士ママのレビューを参考に、自宅でも実践してみよう!
「遊び=訓練」という感覚で、毎日の生活に楽しく取り入れてみてくださいね。