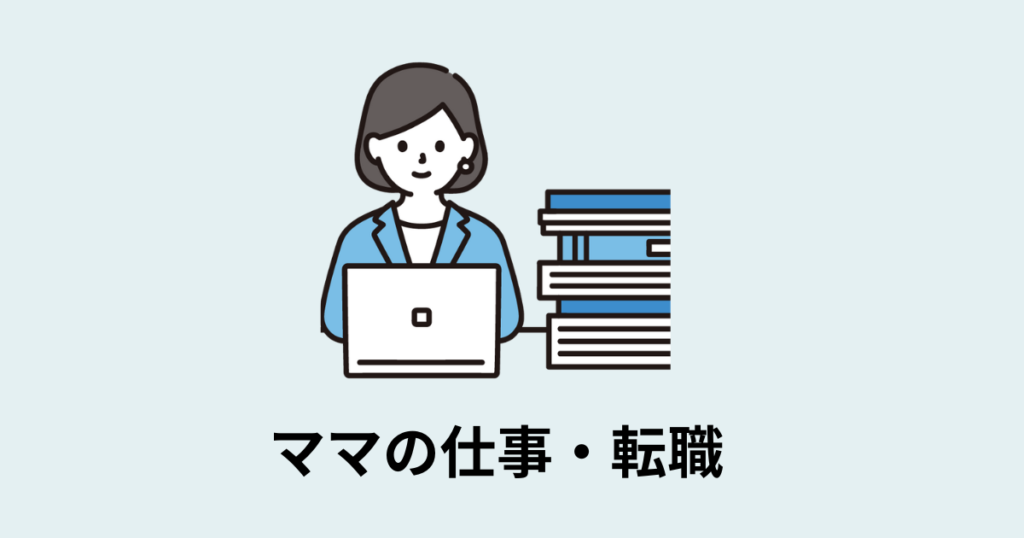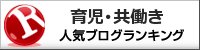クリスマスが近づくと、毎年悩むのが「子どもへのプレゼント」ですよね。
特に5歳、6歳くらいになると、自分の好みや得意・不得意がはっきりしてくるので、選ぶのが難しくなる時期でもあります。

そこで今回は、作業療法士ママの視点から、子どもが喜ぶだけでなく、成長にも役立つプレゼントを厳選して紹介します。
また、ゲームソフトをあげようか迷うという方にも、ゲームをプレゼントする時の注意点をまとめました。
実際の口コミや評価が高く、長く遊べるアイテムを中心にまとめました。
これを参考にすれば、今年のクリスマスもきっと笑顔いっぱいになります。
5歳・6歳の子どもが喜ぶプレゼント選びのポイント

「できた!」を感じられるおもちゃを選ぼう
5〜6歳の子どもは、自分で何かをやり遂げた達成感を感じられるおもちゃが特に喜びます。
完成したときの満足感は、自信や集中力を育む大切な要素です。
たとえばブロックやパズル、工作系のおもちゃは、遊びながら達成感を味わえるのでおすすめです。
“遊びながら学べる”知育系はコスパが良い

この年齢は好奇心が旺盛で、遊びながら学ぶことに興味を持つ時期です。
数や言葉、色彩感覚を伸ばす玩具は、長く使えるのもメリットです。
知育玩具は一度買えば数年使えるものも多く、プレゼントとしての価値も高いです。
キャラクター×実用性アイテムもおすすめ

お気に入りのキャラクターがついたアイテムは子どもに喜ばれますが、保育園や外出時にも使える実用性があるものだと、親としても助かります。
キャラクターと実用性を両立したプレゼントを選ぶと、子どもも親も満足できます。
子どものタイプ別おすすめプレゼント早見表
子どものタイプでプレゼントを選ぶというのも考えた方が良いです。
こうなってほしいと思って選んでも結局使わないということも考えられるので、その時に好きな物をあげる方が活用できます。
| タイプ | 向いているおもちゃ | 育つ力 |
|---|---|---|
| 集中して遊ぶのが好き | レゴ・LaQ・ビーズ系 | 手先・空間認識・集中力 |
| 外で体を動かすのが好き | トランポリン・バランスボード | 体幹・バランス感覚 |
| 想像力が豊か | おままごと・キッチンセット・絵本 | 創造性・社会性 |
| 学び好き・観察タイプ | 図鑑・カメラ | 知識欲・観察力 |
| ゲーム好き | Switchソフト | 問題解決力・協調性 |
ゲームをプレゼントするときに気をつけたいこと

「スイッチをプレゼントしたいけれど、依存しないか不安…」「ゲームばかりして前頭葉の発達に悪影響では?」と感じるママも多いと思います。
確かに、ゲームのやりすぎは注意が必要です。
特に5〜6歳は「自分で切り替える力(自己抑制)」がまだ育っていないため、使い方のルール作りがとても大切です。
ゲームの前頭葉への影響は「遊び方」で変わる
前頭葉は「感情のコントロール」「集中」「計画」「切り替え」などを司る脳の部分です。
ゲームそのものが前頭葉を育てないわけではありません。
むしろ、ルールを理解し、順番を守り、課題をクリアしていく過程は、前頭葉を働かせる行動でもあります。
ただし、長時間ダラダラと続けてしまうと、「報酬系」と呼ばれる“もっとやりたい”欲求を強く刺激してしまい、結果的に注意力や切り替えが難しくなることもあります。
ゲームを安心して遊ばせるための工夫
- 1日30分など時間を決める
→ タイマーを使って「おしまいの時間」を可視化すると切り替えがスムーズ。 - 「一緒にプレイする時間」をつくる
→ 家族でプレイすると、社会性・協調性を学べる。 - ご褒美化しすぎない
→ 「○○したらゲームしていい」ではなく、「家族で楽しむ1つの時間」として扱うと依存しにくい。 - 身体を動かす時間も確保する
→ 外遊びや体幹遊びとバランスをとることで、脳の発達を促せる。
ゲームは「悪」ではなく、使い方次第で学びにもなる道具です。
親がルールを決め、子どもがそれを理解して守る経験そのものが、前頭葉の発達につながります。
家族で“コントロールできる遊び方”を身につけていくことが、今後のデジタル社会を生きる力にもなります。
我が家のルール詳しくは下記の記事で書いています。
【ゲーム依存にならないためのルール決め】5歳から親子で楽しめるゲームとの付き合い方と小学校1年生におすすめのゲームソフトはどれ?
【2025年版】5歳・6歳が本当に喜ぶクリスマスプレゼントランキング10選

男女共通で長く遊べるおもちゃや、知育効果の高いアイテムを中心に選びました。どれも口コミで人気が高く、クリスマスに喜ばれること間違いなしです。
第1位:レゴ(LEGO)クラシックシリーズ
対象年齢:4歳〜
発達効果:想像力・手先の巧緻性・空間認識
選んだ理由: パーツが多く自由度が高いため、兄弟で一緒に遊ぶことも可能です。集中力や創造力を育むのに最適で、長く遊べるのも魅力です。

レゴデュプロはもっと前に買っておいても長く遊べます。
5,6歳になって手の器用さが追い付いてきたり、集中力がついてくるとレゴクラッシックがおすすめ。
もっと理解力が深まってきた年齢では、マリオシリーズやロボットなどもあり、現実場面でのプログラミング要素なども加えることができます。
レゴは長く遊べるのが魅力です。
第2位:スイッチソフト「スーパーマリオワンダー」

5歳でゲームははやい?ゲームでばかり遊ぶのが心配というママもいるかもしれません
けれど、ゲーム自体は使い方を間違わなければ、必ずしも悪というものではないです。
対象年齢:5歳〜
発達効果:問題解決力・協調性(家族プレイ)
選んだ理由: マリオシリーズは鉄板の人気。家族で一緒にプレイできる点も高評価です。ゲームを通して協力する楽しさを学べます。
特にマリオワンダーはキャラクターによって難易度が調整できて小さい子も一緒にやりやすい仕様になっています。
ヨッシーを使って、慣れてきたらマリオなど自然と段階を踏んで遊べるのでおすすめです。
第3位:アクアビーズ or アイロンビーズ
対象年齢:5歳〜
発達効果:手先の巧緻性・色彩感覚
選んだ理由: 色を選んで形を作る工程は集中力を高めます。完成した作品は飾る楽しみもあり、子どもも満足できます。

水で簡単にできるので火傷の心配もありません。
日本ではアートに対しての、遊びが少なめの傾向にあるので、色彩感覚を鍛えておくことは大切です。
第4位:LaQ(ラキュー)ベーシックシリーズ
対象年齢:5歳〜
発達効果:構成力・空間把握力・創造性
選んだ理由: 立体構成遊びができるので、手先の発達だけでなく、空間認識能力の向上にもつながります。長く遊べる知育玩具としておすすめです。

手先が器用な子なら、5,6歳でもできると思います。
不器用な子にはマグネットタイプのブロックがおすすめです。
第5位:図鑑NEO+DVDつきセット(恐竜・動物など)
対象年齢:4歳〜
発達効果:好奇心・知識欲
選んだ理由: 読むだけでなく、DVDで映像としても楽しめるので、知識を自然に吸収できます。特に恐竜や動物はこの年齢の子どもに大人気です。

クリスマスに興味のある図鑑などをあげると喜びますよね。
おもちゃ以外をあげたいなと感じているパパ、ママにもおすすめ。
第6位:キッズカメラ(子ども用デジカメ)
対象年齢:5歳〜
発達効果:観察力・表現力・自己肯定感
選んだ理由: 自分で写真を撮る体験は、観察力や創造力を刺激します。作品を家族に見せることで自己肯定感も育めます。

子どもの見えている視点が大人もみられるので大人も面白いです。
一緒に構図や取り方など工夫して、コミュニケーションをとる手段にもなりやすいですね。
第7位:トランポリン・バランスボード
対象年齢:5歳〜
発達効果:体幹・バランス感覚・運動発達
選んだ理由: 冬の運動不足解消に最適。室内でも安全に体を動かせるので、雨の日や寒い日でも遊べます。
子どもの姿勢を鍛えておくことは大切です。
詳しくは下記の記事をご覧ください。
子どもの姿勢が悪い!家庭でできる机・椅子・遊びの工夫と作業姿勢と安楽姿勢を知ることの重要性
第8位:おままごとキッチン or 工具セット
対象年齢:3〜6歳
発達効果:想像力・社会性・役割理解
選んだ理由: ごっこ遊びを通して会話力や社会性が育ちます。男女問わず楽しめるのも魅力です。

工具セットのおもちゃはごっこ遊び要素だけでなく、力をいれながら回す、押し込みながら回す、力加減を調整するなど日常では経験しにくい動きが経験できるという点でも魅力的です。
第9位:絵本「クリスマスのふしぎなはこ」ほか季節絵本
対象年齢:3〜6歳
発達効果:想像力・情緒理解・読解力
選んだ理由: 寝る前の読み聞かせにぴったり。親子で特別な時間を共有でき、心の豊かさも育めます。

プレゼント+アルファで絵本をあげるのもとてもおすすめ。
クリスマスのふしぎなはこは温かみのある絵と、男の子の日常が描かれている中にも、クリスマス感のある作品です。
クリスマス前から読みだす方が良いかもしれません。クリスマスのドキドキやワクワクが増すかもしれません。
第10位:マグフォーマー(磁石ブロック)やピタゴラス
対象年齢:3歳〜
発達効果:立体構成・集中力・創造性
選んだ理由: STEM教育として人気が高く、兄弟で一緒に遊べる点も魅力です。磁石で自由に形を作れるので、想像力が広がります。
番外編 キャラクター×実用グッズ
我が家はスパイダーマンにはまっているんですが、意外にキャラクター物って値段も高いですよね。
この際、セットにして好きなキャラクターの実用グッズをセットにして送ると、子どもも親もとても実用的ですよ。

お気に入りだからこそ、準備が早くなったり、大事にしようと思う気持ちが育ちます。
プレゼントを渡すタイミングと演出アイデア

サンタさん演出でワクワク感をアップ
手紙や足跡、ラッピングにひと工夫するだけで、子どものワクワク感は格段にアップします。
小さなサプライズを添えるだけで、特別な思い出になります。

我が家では去年一緒にクッキーを作り、サンタさん用に置いておきました。
朝になったらちゃんと食べてくれていました(笑)
兄弟がいる家庭でのクリスマスプレゼントを渡す時の工夫
① 「公平」より「納得感」を意識する
兄弟間でまったく同じものを用意しても、子どもは意外と納得しないことがあります。
大切なのは、“平等”よりも“納得感”です。
たとえば、
- お兄ちゃんには「長く使えるレゴ」
- 弟には「今すぐ遊べるトミカ」
といったように、年齢や発達段階に合った“自分のためのもの”を選ぶことが大切。
また、「サンタさんは○○ががんばっていたことを見てたんだね」など、プレゼントの背景にその子らしさを結びつける声かけをすると、比べっこになりにくくなります。
② 一緒に遊べるプレゼントを“もう1つ”用意する
兄弟それぞれのプレゼントとは別に、「家族みんなで使えるもの」をひとつ加えるのもおすすめです。
たとえば、
- ボードゲーム(ドブル、ブロックスなど)
- ジグソーパズル
- おままごとや工作キット
共通のプレゼントがあると、「自分のがいい・悪い」よりも「一緒にやろう!」という雰囲気に変わります。
結果的に兄弟喧嘩が減り、家族の時間も増えます。
③ 「渡すタイミング」と「演出」も大切
同じ時間にプレゼントを渡すと、開封の瞬間に気持ちがぶつかりやすくなることも。
年齢差が大きい場合は、少しタイミングをずらすのも一案です。
たとえば、
- 先に下の子に渡して上の子がサポート役になる
- 朝と夜で渡す時間を分けて特別感を演出する
といった工夫も効果的です。
また、親が「比べる」ような言葉をうっかり言わないことも大切です。
「こっちは高かったのに」「こっちはすぐ飽きるね」などの言葉は、子どもの“自尊心”を傷つけてしまうことがあります。
どの子にも「あなたにぴったりなプレゼントだね」と伝えてあげましょう。
+α:サンタ設定を兄弟でどうする?
兄弟間で年齢差があると、「サンタさんってほんとにいるの?」という問題も出てきますよね。
そんな時は、上の子を“サンタのお手伝い役”に任命するのがおすすめ。
秘密を共有することで、
- 下の子を思いやる気持ち
- 成長への自覚を促すことができます。
兄弟の関係もぐっと良くなるクリスマス体験になりますよ。

兄弟へのプレゼント選びは、「金額のバランス」よりも「気持ちのバランス」。
年齢や興味の違いを尊重しながら、それぞれが“自分のプレゼント”に納得できる工夫をすることが一番大切です。
「家族で一緒に楽しめる時間」こそが、最高のクリスマスプレゼントになるでしょう。
プレゼント後の「一緒に遊ぶ時間」が大切
どんなに良いおもちゃでも、一緒に遊ぶ時間がないと満足度は半減します。
親が一緒に遊んであげることで、子どもはさらに楽しめますし、発達支援としても効果的です。
まとめ|「好き」と「成長」がつながるプレゼントを選ぼう

5〜6歳は遊びながら成長する黄金期です。
単なる流行だけでなく、「子どもの興味」と「成長」を意識してプレゼントを選ぶと、長く遊べて学びにもつながります。
子どもをよく観察して、何が好きなのか、どんなことに興味がるのか考える時間も親の醍醐味ですよね。
ただ、どんなプレゼントを渡すのが良いのか迷ってしまう時の参考になればと思います。
今年のクリスマスは、笑顔いっぱいの時間を子どもと一緒に過ごしましょう。
こちらもおすすめ