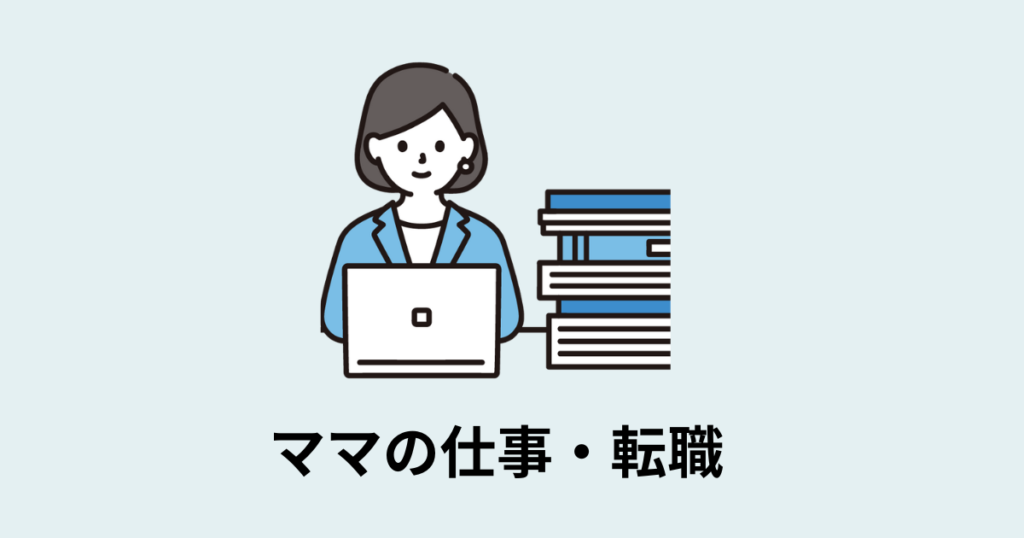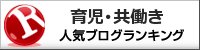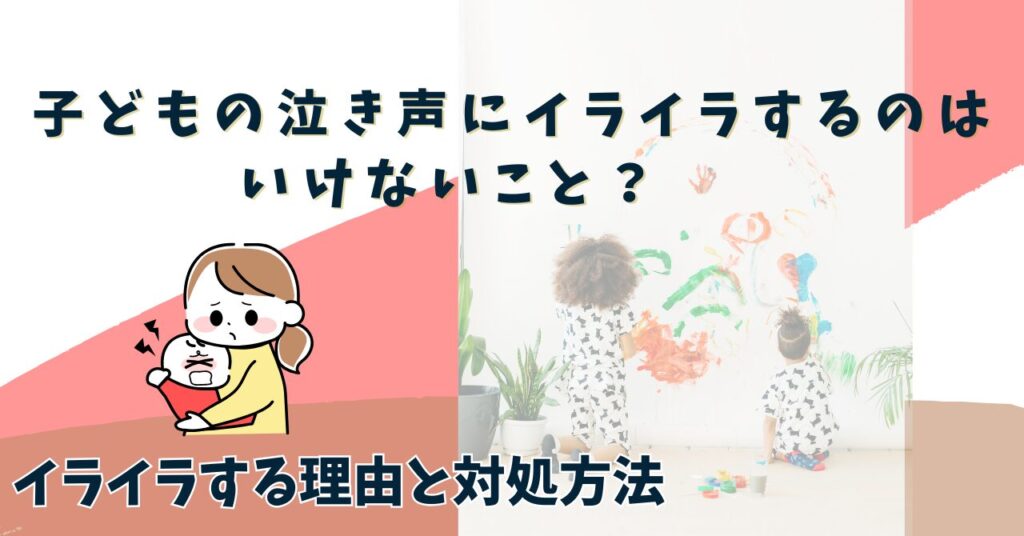
赤ちゃんの育児でも、幼児の育児でも、子どもの泣き声にイライラしてしまうことってありますよね。

私も一人目を育てている時に、元々静かな状態が好きな気質もあって、正直、泣かれるとうるさくてストレスでした。
でも、今考えるとそれほど自分も追い詰められていたのかなって思います。
イライラすることすらいけないことなの?母親失格?って不安に思っているママもいるかもしれません。
でも、だれでも毎日毎日、横でうるさく泣かれるとストレスになって、自分しか大人がいない場合に、責められているように感じることってあるんじゃないかな…。
そういう育児に追い詰められている人に届いてほしい記事です。
こどもの泣き声にイライラする理由

子どもの泣き声は耳障りなのが普通
子どもの泣き声にイライラする理由は、子どもの泣きごえが実際に親の心拍数を上昇させるからです。
そして、子どもの泣き声を聞くことで、ストレスホルモンが出されることもわかっています。
子どもの泣き声は危険や不快感を知らせるための信号の為、特に親である場合は子どもの安全を確保するためにストレスを感じやすいです。
そして、子どもの安全を守ることにつながります。

赤ちゃん育児の場合ってほんとうに、ちょっとしたことで死んでしまうのではないか?っていう恐怖心が常に付きまといますよね。
危険なことを知らせてくれる泣き声にストレスを感じるのは当然と言えば当然ですよね。
強いストレスに感じていることは、親の証拠なのかもしれません。
赤ちゃんの泣き声は通常、3000Hzから5000Hzの高周波数帯域です。
そのため、人間の耳にとって非常に敏感な音域です。
音に敏感な人にとっては物理的にストレスなんですよね。
子どもの泣き声は意思表示の一つ
特に赤ちゃんのうちは、言葉を持ちません。
そのため、泣くことがあかちゃんの意思表示です。
赤ちゃんは様々な理由で泣きます。
赤ちゃんが泣く理由例えば
- 空腹
- おむつなどの不快感
- 暑い、寒い
- 音にびっくりした
- 眠い
- ゲップやおならがうまくできない
- どこか痛い
- 虫に刺された
など…
赤ちゃんは泣くことが仕事と言われるように、泣いて自分の意思を伝えようとします。

空腹とか痛いなどは、命の危険だな~ってわかるけど、眠くて泣いてるって寝たらいいのにって大人は思ってしまうこともありますよね。
眠りがうまくできるようにサポートしていくの難しいですしね。
夜泣きについての体験談はこちら。
不快感を取り除いて、安心感を与えてあげれば泣き止むことが多いですが、親としてはなかなか泣き止まないと焦ってきます。
原因がわからないことにイライラしてしまいます…。
ママが子どもに責められているように感じる理由

親であってもストレス耐性は様々です。
そのため、感情のコントロールがしにくい人と、しやすい人がいて、感情コントロールがしにくい人にとって、子どもの泣き声はストレスになりやすいです。
また、文化的な要因もあります。
特に日本では子どもの泣き声に対する声は厳しい物であることが多いです。
それはママ自身でも、そういった考えが定着しているからこそ、子どもに責められていると感じる場合もあります。
公共の場で他の人からの目線も気になりますが、二人きりでも、泣かせてはいけないってママ自身が思っていることも多いですよね。
また、実際に公共の場ではひどい言葉を投げかける人もいます。
ただ、そういう人ばかりではないということは知っておいて欲しいなと感じます。

なかなか声をかけにくい世の中ですから、声は掛けませんが、他のママが公共の場で焦っていると心の中でママ頑張れ~ってパワー送ってしまいますよね。
子どもの泣き声に対する具体的な対処方法
子どもを抱っこする
子どもの安心感としても抱っこは有効な手段です。
何が不快かはわからないけれど、なんとなく不安という理由で泣いている赤ちゃんは抱っこされることで、安心して泣き止むことがあります。

ただ、抱っこで肌に触れあうことは赤ちゃんだけでなく、ママの安心感にもつながります。
作業療法でも、認知症の人に対してはタッチケアという方法を用いることがあります。
「触れる」と言う行為自体が、人間に安心感をもたらせてくれます。
モチモチの赤ちゃんの肌にママも癒されるので、感触だけを楽しみましょう。
子どもの泣き声から離れる

泣き声がどうしても耳障りで、頭痛がし始めるなどの症状がでることもあります。
そういう時には赤ちゃんの安全を確保したうえで、いったん離れましょう。

私も少しだけ違う部屋に行き、自分の心が整ったらまた赤ちゃんのそばに行くということをしたことがあります。
少しだけでも離れると気分がかわります。
イヤフォンやイヤーマフをして音声を調整する

イヤフォンをするなんて…って思うかもしれませんが、これは泣き声がストレスになっている親に対しての対処方法として注目されている方法です。
赤ちゃんの泣き声は通常100デシベル以上の音量に達することがあり、長時間聞くと難聴のリスクがあるほどです。
そのため、イヤーマフやノイズキャンセリング機能のあるイヤフォンを使い、親の耳に届く赤ちゃんの声を軽減させることで、ストレスが緩和する効果があるとされます。
ノイズキャンセリング機構は泣き声は小さくしつつ、必要な音は聞き取れるためストレス緩和に役立ちます。

私もどうしてもストレスだなっていう時にはイヤフォンのノイズキャンセリング機能を使っていました。
かなりストレス軽減になると実感しました。
子どもの泣き顔を写真で撮る

こどもの泣いている顔ってよくみると面白いんです。
泣いている時って余裕がなくなるからこそ、少し冷静になって泣き顔を写真に収めてみると「将来こんなことがあったな~って思うのかな~」と今じゃない場所に心を馳せることができます。
深呼吸をする
ストレスがかかっている時は呼吸が浅くなりがちです。
そのため、一旦深呼吸をすることでリラックス効果が得られます。
笑顔になると楽しくなるというのと同じで、深呼吸をすると心がほぐれます。
育児のストレスをうまく発散させる

育児はストレスだらけですよね。
でも、そのストレスとどう付き合っていくのかという点で、自分自身がストレスの発散方法を獲得するチャンスです。
できないことを受け入れる
完璧でないといけないという考えから抜け出しましょう。

家事や育児頑張ったらきりがありません。
だから「こんなもんでいいよね」「できてないこともあるけどいいよね」とできないことを受け入れましょう。
世の中に自分ができないことっていっぱいありますよね。
私はフルマラソンも走れないし、上手に歌うこともできない、薬を開発することも、模試で100点をとることも…。
みんなできないことがあって当たり前です。
育児になると急に、なんとなく「みんなできているのに…」って思いがちです。
みんなできていない部分を誰かに助けてもらったり、子どもに助けてもらったりしながら生きているんだと思います。
誰かと話をする
大人と話をするのもストレス発散になりますよね。
話をよく聞いてくれるような人と、少しの時間つながってみると良いかもしれません。

オンラインでランチをしたことがあるのですが、とってもいいですよ。
少しだけでも育児じゃない世界に連れて行ってくれます。
オンラインなら2人か3人くらいがベストですね。
独り言を上手に言う
赤ちゃんと二人きりの場合、ほぼ独り言ですよね(笑)
独り言ってじつはストレス発散の機能があるのを知っていますか?
例えば「疲れた~」「あ~もう嫌だな~」など自分の気持ちを吐き出すことで、一人なのになんだかストレス発散になります。
だから、独り言が多くなってもいいんです。
家事は思いっきり手を抜く
家事は赤ちゃんが生まれる前から手を抜いておくのがポイントです。
産休中でやることがないからといって、家事に力を入れていると、赤ちゃんが生まれてから「家事ができない」とストレスになることがあります。
家事の手を抜き方がわからない方はこちらをご覧下さい。
【楽するために家事でやめたこと】できるだけ楽に・効率よく暮らしたい私の家事削減術。これをやめたら劇的な効果があったと感じた5選
【やめたことリスト】ズボラ民の私が、やめて良かったキッチン周りの家事。
一人時間をつくる

一人の時間って大事ですよね。
私も育児でストレスが溜まってきたときは、夫が帰ってきてから、一人で公園のベンチですごしたことがあるんです。
もともと一人が好きな性格もありますが、自分のペースでできるって幸せです。
一人でトイレに行けること、一人で歩くことができること、一人でコーヒーを飲めること。
こういう些細な一人時間が育児をしているとどうしても必要になります。
自分のペースでできないってかなりストレスですよね。
少しでも自分のペースでできる時間があれば、少しはストレスから解放されるかもしません。
誰も預ける人がいない時には、一時保育など利用するのは悪い事ではありません。
【育児ストレスでもう限界!】すぐできる、実際場面での子育て中ストレス発散方法9選
まとめ 子どもの泣き声でつらくてもはママ失格じゃない

いつも子どもに向き合って、まじめに頑張っているからこそ、辛く感じているんだと思います。
周りの声もあるかもしれないけれど、自分が一番自分を責めてしまっているのかもしれません。
そんな時には私はとりあえずできることをするしかないし、できないことはいっぱいあるという考えを再認識するようにしています。
イライラしないようにするのは無理です。
だってイライラするんだから。
そんな時は自分に余裕がないのかな~と思って、まずは自分を癒してあげて下さいね。
親になったから急にすべてができるようになるわけない。
try&errorで人生を楽しむ術を探していけるといいなと思っています。